|
|
この記事は “The Miracles of Exodus: A Scientist’s Discovery of the Extraordinary Natural Causes of the Biblical Stories”(出エジプトの奇跡:聖書物語を通常では見られない自然的プロセスであると見なす見解を裏付けるある科学者の発見)という英文の本の概略と評価です。コリンJ.ハムフリズの論点を多少修正する筆者の所見をも加えました。全体的に言えば、ハムフリズの研究は出エジプト物語の細部の多くに関連して、伝統的な見解を考え直す強力な論拠となりました。ハリウッドの映画ばかりでなく、多くの聖書注解書に描写されているストーリーには、内部的に一貫性に欠けている面が多くあります。ハムフリズ博士が提出する証拠は、出来事の展開に対する神の奇跡的な支配を保ちながら、出エジプト物語を一貫性のある流れに変えて行きます。この記事では取り上げなかったのですが、他にも興味をそそる話が数多く載せられていますので,この本を是非お薦めしたいのです。しかし、残念ながら日本語版はありません。英語版はこのアドレスで注文できます。Amazon それでは、伝統的な見解の主な問題点をリストしましょう。 (1) シナイ山の地理的な位置:伝統的には、聖書のシナイ山はシナイ半島南部にあるジェベル・ムサ(アラビア語で「モーセの山」という意味)という山であると考えられています。しかし、この山は聖書の記述にはあまりそぐわないのです。もっと有望な山がないのでしょうか。 (2) 出エジプトのルート:最初の目的地はシナイ山でしたので、イスラエル人が辿ったルートはシナイ山の位置づけと深く関連します。紅海(葦の海)を渡ったのはどこだったのでしょうか。「紅海」が何を指しているか、また、その海を渡った場所はどこかという点でも、伝統的な考え方は聖書の記述と大きく異なります。3000年以上も経った現在、確信を持って、実際のルートを決定できるのでしょうか。 (3) 出エジプトの年代:列王記上6:1によると、「ソロモン王が主の神殿の建築に着手したのは、イスラエル人がエジプトの地を出てから四百八十年目」でした。聖書の記述と考古学的なデータ両方を合わせる、その年代は紀元前966年だったと分かります。従って,それから480年を遡ると,出エジプトの年代は紀元前1446年となります。しかし、圧倒的多数の証拠はこれより150年〜200年後の大王ラメセス二世の時代を支持し、大半の学者がこの年代を受け入れています。これらの矛盾する年代を調和することができるでしょうか (4) 参加した人数:民数記1:46によると、20才以上の男性の人数は603,550人だったので、これから推測すると,全人口は200万人以上になります。このような大規模な人数は,大半の現代人にとっては、単なる神話でないとすれば、物語全体が極めて誇張されていると見なすのです。聖書本文の他の細部も、このような大規模な人口にそぐわないのです。ですから、話全体が内部的な一貫性を持つものとなるためには、これらの数字をどのように理解すべきでしょうか。 この重要な出来事の首尾一貫した全体像を描き出すためには、その他の多くの細部をも考慮する必要があります。それで、以上の問題点を一つずつ取り上げて、物語全体を見て行くことにしましょう。 まず,奇跡の本質を一般論として考えてみましょう。奇跡は二つの範疇に分けられます。一つは、神が自然的プロセスを利用して、そのタイミングと規模を操ることによって起こった奇跡、そして、二つは、御自分が創造した自然法則を越えて行われた、全くの超自然的な奇跡です。この二つ目の範疇の例として、キリストの復活(また、キリストが甦らせた人たち)があげられます。神が定められた自然法則の枠組みの内部で自然的プロセスが超自然的に導かれるだけでは、このような奇跡は起こり得ないのです。 しかし、出エジプトの奇跡に関しては,全てではなくても、ほとんどの場合、第一の範疇に入っていると理解できます。要するに,目的を果たすために、神が自然現象のタイミングと規模を操られたということです。例えば,最後の災い(長男の死)は例外かもしれませんが、エジプトの10の災いは超自然的にコントロールされた自然現象として理解できます。 ハムフリズ氏の解説は、出エジプトの最後の出来事である、約束の地に入るヨルダン川渡河(ヨシュア記3〜4章)から始まります。川が洪水のレベルあったにもかかわらず、イスラエルの民が渡れるように、流れが突然に止まりました。これは天使たちの働きによって、上流の水が重力の法則に従わなくなって流れが止まったというような出来事として理解すべきでしょうか。聖書本文では、そのような出来事として紹介されているのではなく、実際は、ヨシュア記3:16によると、「川上から流れてくる水は、はるか遠くのツァレタンの隣町アダムで壁のように立った」のです。(日本語の「壁のように立った」と翻訳されたヘブライ語は「積み重なった」という意味だけで、重力の法則に従わない「壁」のような水という意味はありません。)これは渡河した場所から30kmほど北の方であったと推定できます。その場所では、川を一時的にせき止める地滑りが歴史的に知られているのです。1927年には、そのような地滑りがヨルダン川を20時間以上せき止めた例が実際にあります。 原文では、この奇跡がどちらのタイプであったかには直接触れていませんが、川の水が「積み重さなった」場所が見えないほど遠くにあったことから考えれば,それは地滑りのような物質的現象によることだったと推定できます。しかし、そのタイミングが重要でした。はるかに上流で川が偶然にせき止められて、「祭司たちの足がヨルダン川に入る」とたんに川の水がなくなる確率はあまりにも小さいので、そのことを神様が行なった奇跡として受け止めることは妥当なことです。それは、特に,神が前もって、ヨシュアにそうなると予告されたためです。「川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は、壁のように立つであろう。」(ヨシュア記3:13) 同様に、出エジプト物語の他の奇跡の大部分も,神がまったく奇跡と思えるような仕方で、自然現象のタイミングと規模をコントロールされたものとして説明できます。聖書本文にある描写は、神のコントロールの下に導かれた自然現象の一つです。そして、エジプトにもたらされた一連の災いにおいて見られるように、それぞれの奇跡が互いに深く関連しているのです。 シナイ山の地理的位置それでは、これらの課題を一つずつ取り上げて,よりつじつまが合うストーリーを組み立てて行きましょう。最初に,シナイ山の位置を検討しましょう。出エジプト記によると、モーセはエジプト人を殺した後に、メディアン地方に逃げて行きました。メディアンは現在のサウジアラビアの西部にある地域で、アカバ湾を隔てたシナイ半島の対岸にあります。そこで地元の女性と結婚して、義理の父の羊を飼いました。 メディアンの羊飼いたちは「荒れ野の奥」(出エジプト3:1)にあった山々に連れて行く習慣がありました。シナイ山は後にシナイ半島と呼ばれた地域にあったという考え方が古くから根付いていましたので、モーセは、アカバ湾を回って群れをシナイまで連れて行ったと推定されました。もし,聖書本文で「海の反対側に」と書いてあるなら、そういうふうに考えるのは妥当でした。しかし、実際はそうではなく,直訳すれば、「砂漠の向こう側」と書いてあります。そして、群れを「荒れ野の奥」まで連れて行く目的を考えれば(つまり、牧草を探すために)、アカバ湾の反対側にあるさらに乾燥しているシナイ砂漠まで連れて行くことは道理にかなわないのです。 では、この「荒野の奥」とはどこを意味するでしょうか。シナイ山がシナイ半島にあるという古い伝統を抜きに考えると、「砂漠の向こう側」(荒野の奥)はモーセがいたメディアンの砂漠の反対側にあると結論するのは道理にかなっています。その正確な場所はもちろん分かりせんが、「メディアンの祭司」であった義理の父エテロの家族との生活から、「ヒスマ」(Hisma)と呼ばれる砂漠の端にあった場所だったと推測できます(図1参照)。一番可能性のある場所はアカバ湾の奥から三日間の旅程に位置するマディアン近辺でした。そこは、比較的水の多いところでした。 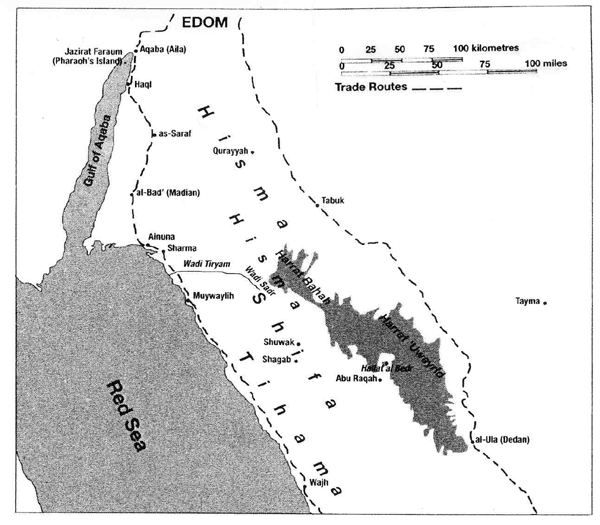 図1 そこからであれば、「荒野の奥」は南東の方向にある火山地帯になります。そして、ハムフリズ氏は、聖書に記述されているシナイ山の描写と大変によく合致する山として、「ベドゥル山」という活火山を特定しました。さらに、この一風変わった山までの推定されるルートは、出エジプトの詳細とよく合致します。しかし、その結論を裏付ける数多くの証拠を分析する前に。まず、上記の課題3と4(出エジプトの年代と参加した人数)を取り上げましょう。 出エジプトの年代すでに述べたように、列王記上6:1によると、ソロモン王が神殿の建築に着手したのは、出エジプトから480年後のことだったので、これは出エジプトの年代のかなりはっきりした決め手となりそうです。しかし、ここで考慮しなければならないのは、原文の著者とそれを読んだ当時の人たちはこのような数字をどのように理解したかということです。古代イスラエル人は現代人の私たちと同じように数字を利用したのでしょうか。明らかにそうではありません。最近の研究は古代中近東のかなり違った数え方にある程度の光を当てるようになりました。 それによると、古代中近東の文化では、現代の私たちが使っている十進法ではなく、六進法を使っていました。六進法では,7、8と9に相当する一桁の数字はありません。さらに、0は後に発明されたものですから、古代の記数法には0は使用されていませんでした。それで、6の次の数字は「11」となります。しかし、この「11」は十進法に換算すると7です。私たちが普通使用している十進法での480年は、当時使用されていた六進法では288年となるのです。 後の時代の聖書記者は明らかに今日と同じ十進法を使っていましたが、初期の記録に出てくる数字に関する難問は、このような数え方の違いに関係している可能性があります。歴史的な記録そのものは目撃者から口述で,また,何かの文書として正確に伝えられて、後に現在の聖書にまとめられました。しかし、その中に含まれていた数字の適切な調整がされなかった可能性が高いのです。 ハムフリズ氏は、この「480年」と他のすべての証拠が示している約300年という矛盾を解決するためにもう一つの提案をしました。聖書の用法では、一つの「世代」は一般的に40年とされています。ですから、一つの世代を40年と考えるなら,480年はちょうど12の世代となります。しかし、実際には,世代交代は平均的に40年をかなり下回ります。ですから、もし、原文の著者が40年を一世代として、「480」という数字を12の世代という意味で使ったのなら、実際の年数は300年程度となります。ソロモンによる神殿建設の時代の祭司長からモーセの兄弟アロンまで遡る系図は14世代であったことはこの解釈を裏付けます。というのは、出エジプトの時点で、アロンはすでに2世代に当たる年齢に達していましたので、ソロモン神殿建設から出エジプトまでの年代は、ちょうど12世代となります。 また、数字に関する未知の古代の概念があって、それがこの問題を解決してくれるかも知れません。どんな解決方法にせよ、その他の証拠がもっと後の年代を指しているので、列王記上6:1の「480年」に現代の数字の記数法を適用して、文字通りの数字として解釈すべきではないことは明白であるように思えます。出エジプト記1:11に、奴隷であったイスラエル人が「ファラオの物資貯蔵の町、ピトムとラメセスを建設した」と明白に書いてあります。考古学的発掘調査による結論によると、その豪華な町であったラメセスは紀元前13世紀にあった66年も続いたラムセス2世の統治の時代に建設されたのです。従って,出エジプトの一番可能性が高い時期としては、紀元前1300年と1250年の間です。 参加した人数出エジプトに加わったイスラエル人の数は、数字におけるもう一つの問題です。文字通りの数字を実際のイスラエルの人口として理解するならば,あまりにも大きくてありえないことと思えるばかりでなく、本文の他の記述とも矛盾してしまいます。民数記1:46に記述されている603,550人の兵士に女性や子供を加えると,全人口は200万〜300万人であったはずです。しかし、出エジプト記23:29-30によると、イスラエル人の数が少なすぎたため、神は「約束された地」から敵を「徐々に追い出す」ことにされました。また、申命記7:1によると、イスラエルの民「にまさる数と力を持つ七つの民」を「約束された地」から追い出されました。そして、申命記7:7には、イスラエルは「他のどの民よりも数が多かった」のではなく、「他のどの民よりも貧弱(少人数)であった」と書いてあります。ですから、民数記の人数を文字通りに受け取れば、イスラエルが征服した地域の全人口はおよそ2000万人であったはずです。それは現在の人口よりはるかに多いのです。紀元前1000年には地球全体の人口はおよそ5000万人しかいなかったと推定されています。(http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html) その上、聖書本文に記述されている出来事が実現可能であったということは、文字通りの数字よりはるかに少ない人数であったことを示唆します。例えば,紅海の横断は夜で、暴風の中にもかかわらず数時間で終わりました。渇いた地の幅は、短い時間内に渡った人間と動物の数の決め手となります。しかし、海が風によって何キロもの幅に分けられたと推測しない限り,短い時間内にそんなに多くの人間と動物が渡ることは不可能です。また、砂漠地帯の限られた資源を考えると、神が毎日のように超越的奇跡を起こされたと想定しない限り,200万人以上の人数を長い間養うことは極めて考えにくいことです。しかし、神が自然現象を超自然的に導かれたことは、聖書本文が示唆しているのですが、200万人を超える人数が荒野で何十年も生活をするにはまったく十分ではなかったことでしょう。 この難問を解決するハムフリズ氏の提案は、ヘブライ語で書かれている数字の意味を再解釈することです。その要点は、「千」と翻訳された「エレフ」という単語には、前後関係によって「グループ」や「分団」という意味にもなるということです。例えば、民数記1:21から始まる各部族の人口調査の目録において、ルベン族に「兵役に就くことのできる二十才以上のすべての男子」は「四十六エレフ(と)五百」と書いてあります。これは20才以上の男性の人数でした。私たちが一般的に使っているアラビア数字はまだ発明されていなかったので、このような面倒な形で書かれました。 これを46の分団の合計が500人であったと解釈して、他の11の部族も同じように計算すれば,合計5550人となります。そうすれば、全人口は2万人程度となります。この程度の人数ははるかに「妥当」に思えるのですが,この提案では、解決しなければならない他の問題が出てきます。それぞれの数字は明らかに百の位の概数です。ガド族だけが例外で、45「エレフ」と650人ですが、それでも、中間の50という概数になっているようです。しかし、分団の数は概数とはなっておらず、合計の人数だけを概数にしてしまうのは奇妙です。さらに、分団の平均人数は9.3人ですが、シメオン族の5.1人からガド族の14.4人までの変動の幅があります。 ハムフリズ氏の分析では、自説を支持する聖書本文の証拠がいくつか紹介されています。その中には、民数記3:46に記載されているように、イスラエル人全体の長子の数はレビ族の数よりたった273人多いだけであることが含まれています。レビ族は他の12部族と同じ規模の人数だったと推測できますので、各部族の成人男性の人数は数万人ではなく数百人でなければ、このような数字は道理に合わないのです。また、各部族の人数の下三桁がすべて、200と700の間(000、100,800、900ではない)となる確率(0.6<12>=0.00218)は極めて低いのです。40年後の人口調査(民数記26章)でも全く同じパターンとなるので、このようなことが偶然に起こる確率はさらに低くなります。 最初の人口調査に関しては、各部族の「エレフ」の合計は598となり、その数字の次に来る人数の合計は5550人となります。しかし,民数記1:46ではその合計が600「エレフ」と3550人となっています。従って,ハムフリズ氏の説が有効であるためには、聖書の原文がある種の編集過程において、人数に割り当てられていた2「エレフ」(千)がその前にある分団(エレフ)に移されたと考える必要があります。同じように,民数記26章に記録されている第二の人口調査では、596「エレフ」と5730人となりますが、四つの「千」を意味する「エレフ」が「分団」を意味する「エレフ」の方に移されたことになります。そうすれば、現在のヘブライ語の聖書に書いてある「六百エレフと一エレフ(千)七百三十」人となります。 可能性として考えられることは、モーセが記録した最初の人口調査の結果を記録する時に、「五百と九十と八エレフと五エレフと五百と五十」という書き方をしたのかも知れません。この場合、最初のエレフは「分団」で、次のエレフは「千」を意味したかも知れません。現代に伝わる聖書本文に少なくともある程度の編集がなされていることは明白です。(例えば,モーセの死は自分で記録したことはあり得ないことです。)私たちの手元にあるモーセ五書はモーセから何百年か後に最終的な形となったのですから、編集の段階で扱いにくいそのような数字が「六百エレフと三エレフと五百と五十」(現在の文字通りのヘブライ語)とされたことはありうることです。モーセの時代の人たちは二つの意味を持つ全く同じ単語である「エレフ」の区別が分かっていたのに、異なる記数法を持つ何百年か後の筆記者がその区別を知らないで,このような間違いをした可能性があります。 この説が数字における問題の正しい解決であるかどうかは別にして、オリジナルの記録とそれが旧約聖書に導入されて記載された明細との間に、翻訳上の何らかの問題が生じたようです。弱点がないわけではないのですが、ハムフリズ氏の提案は少なくとももっともらしい説明で、エジプトから出たイスラエル人の数が2万人であることは、記録された旅の詳細と考古学的発掘調査によって明らかにされた当時の人口と合致しています。 エジプトの災いシナイ山の場所と出エジプトのルートというテーマを取り上げる前に、イスラエルの民をエジプトから出させるようにファラオに強要するために、神がエジプトにもたらした一連の災いに関するハムフリズ氏の大変興味深い説を紹介したいと思います。十の災いは相互に無関係ではなく、それぞれの災いはそれに先行する災いと深く関連する自然現象として説明できます。当然、最後の災いであった初子の死を自然現象として説明することが最も困難を伴いますが、ハムフリズ氏はこの点でも有望な提案をしました。 聖書に記述されている詳細とそれぞれの災いの原因となり得る自然現象についての科学的知見を合わせて考えると,十の災いは、神が目的を果たすために総合的にコントロールされた自然現象であったとする見方が濃厚となります。 そのプロセスはナイル川が「血に変わる」ことから始まり,それによって、大量の魚が死にました。この出来事が起こった場所は聖書の記述から割り出せます。それは、イスラエル人がその時にピトムとラメセスを建設していたと書いてあるからで、それらは現代の都市カンティル(Qantir)の近くにあったことが判明しました。そこは地中海から30 kmぐらい内陸にあるナイルデルタにあります。ですから、その災いの被害を被った地域は、この広いデルタに枝分かれした7つの主要な支流の一つでした。ナイル川の氾濫は毎年の夏の終わりから秋の始めに起こり、エチオピア高原から大量の赤い土壌が流れ込んで来ました。ある学者はそのような赤い土が異常に多く流れたことによって、水が血のように赤く染まったのだという説を提案しました。 そのことは、河川の赤い色を説明するかもしれませんが、魚の大量死の説明にはなりません。大量死の原因と考えられるのは、藻類の大量発生によって酸欠になったか、また、ある種の藻類によって発生した致死的な毒素です。「赤潮」とはこのような現象で,条件がそろえば、大量発生によって水が赤く染まるのです。赤潮を引き起こす藻類は、淡水が流れている川には育たないのですが、淡水がよどんでいる川で起こり、特に淡水と海水が混じる河川の河口では一般的に起こる現象です。必要な条件とは、栄養が豊富な暖かい水と豊富な日光だけで、この意味でナイル川のデルタでの赤潮の発生は決して不自然ではないことでしょう。このような現象が最も起こりやすい時期は9月です。この時期に最初の災いが起こったとすれば、タイミングとして3月末〜4月初めに行われた出エジプトに繋がる一連の災いの連鎖にうまくはまります。 「赤潮」が発生して一週間ほど後に,魚の大量死と腐敗が始まったはずです。こうした状況は、その時期に多く生息していた蛙にとっては、極めて不快な環境となりました。そのような環境を避けようとして川から離れ、えさを求めて昆虫を引き寄せる灯の方へと自然に寄って行くので、第二の災いについての記述の通りに,エジプト人の住宅に大量に入ってくることになったことでしょう。 それで、腐敗した大量の魚の死骸と蛙の突然の減少によって、自然に引き起こされたのは何でしょうか。それは、出エジプト記が語る第三と第四の災い、すなわち「ぶよ」と「あぶ」の災いでした。聖書本文では、種類が特定されていませんが、その地域に生息する特有のぶよとあぶであったとすれば、それらは第五と第六の災いに自然に繋がって行きます。 具体的に言えば、「アフリカ馬病」と「ブルータング病」(青舌病)の病原体であるウイルスの感染を媒介する“Culicoides midges”というぶよがいます。それらの病気は聖書に書かれているように、馬や牛のようなひずめのある哺乳類を死なせる疫病です。出エジプト記によると、川からかなり離れていたイスラエル人の家畜には影響がなかったので、被害地域は限定されていました。その上、数ヶ月後にはファラオの軍に馬が十分いたことから考えれば、王国の他の地域は被害を免れたようです。ナイル川の上流にある赤潮が発生しなかった地域では、これらの災いの連鎖が起こらなかったと推定できます。 第六の災いは人間と動物の両方を悩ませた皮膚病でした。申命記28:27-35によると、この「エジプトのはれ物」は最初に足に症状が現れ、それから、体全体に広がって行く皮膚病として描かれています。可能性のある病原体として、人間と動物の両方にこのようなはれ物を引き起こすバクテリアがあります。それは、その地域に生息する「サシバエ」と呼ばれるぶよによって媒介されます。この仮説によれば、第三の災いのぶよと第四の災いのあぶが爆発的に増えたことが、直接に第五と第六の災いに繋がったのです。 ハムフリズ氏の提案によると、ナイル川が氾濫する9月に始まった災いの連鎖は段階的に進行して、12月か1月に第六の災いに至ります。病原体の潜伏時間などを考えると、その災いの連鎖はもう少し速く進むのではないかと思いますが、時間的に不合理ではありません。この説は聖書本文の記述とそれぞれの自然現象がもたらす結果と合致しています。神が御自分の目的を果たすために、タイミングと規模をコントロールしておられるなら、特にそうです。「赤潮」は幾分か遅れて、すなわち川の氾濫期が過ぎて後に起こった可能性もあります。そうであるなら、連続的に起こる災いと災いの間の時間を短縮することができます。 最後の4つの災いは最初の6つの災いと直接的な繋がりはありません。それらは、別の自然現象から始まります。すなわち、第七の災いである雹の災いです。聖書本文によると、時期的に早い亜麻と大麦は壊滅的になり、より遅い小麦と裸麦は回復できる状態でした。ですから、雹の嵐は2月末か3月初めに起きたと推定できます。そのような嵐の被害は局地的ですので、数キロ離れたイスラエル人たちは無事だったことは何も不思議ではありません。 第八の災いであったいなごは一日中吹いた強い東風に運ばれたいなごの大群として描かれています。前日の嵐で土がまだ濡れていたので、卵を産む成虫にとっては、それは絶好の場所となります。出エジプト記によると、雹はイスラエル人がいたゴシェンの地域以外のところに降ったのですが、「エジプト全土」(9:25, 10:15)という表現は現代の地理的な感覚で受けとれられるべきではなく、関係している人たち(エジプト人)が住んでいた地域を意味します。ですから、広い範囲に及んだとは言っても、局地的な現象でした。エジプト人が住んでいない地域がそれほど濡れていなかったとすれば、濡れている砂質の土壌に集中するはずでした。そこは、いなごが探し求めていた絶好の場所であったのですから。第七と第八の災いの関係は、最初の6つの災いの連鎖ほどはっきりしてはいませんが、このような間接的な関係は十分考えられます。 第九の災いは「手に感じるほど」の暗闇として描かれています。それはエジプトのような砂漠地帯では珍しくない現象です。すなわち、激しい砂嵐です。エジプトでは、舞い上がる砂塵はだんだんと少なくなるので、普通は季節の最初の砂塵嵐が一番ひどいものとなります。最初の砂嵐は通常3月に起こるので、出エジプトが3月末か4月初めに始まったことと、タイミング的には合致しているのです。 しかし、この砂嵐が三日間も続いたことは、異常なのです。その年の砂嵐が地域を暗闇に包んだほどの強さに至った理由としては、神が特別に強い風を起こされたことの他に、いなごが地面を露出させたことや前年のナイル川の異常な氾濫によって運ばれた大量の細かい土が地面に積もっていたことが容易に考えられるでしょう。 次は、最後の災いです。これは、自然現象として考えることが最も困難なものです。人間でも動物でも、男子(雄)の初子だけを死なせる現象はあり得るのでしょうか。これは、「死の天使」を通して、社会全体のレベルではなく、個人的なレベルで出来事を操るケースかもしれません。しかし、ここでも、ハムフリズ氏がもっともらしい仮説を立てています。それはエジプト人の宗教的世界観に基づく、彼らの長男と家畜の雄の初子に対する特別な思いと関係があります。動物の初子に関しては、確定的な考古学的証拠はありませんが、その可能性は高く、イスラエル人の場合、出エジプト記13:2やその他多くの旧約聖書の箇所に示されるように,明らかにそうでした。また、動物の初子の死を言及しているということ自体が、他の動物と区別されていたことを意味します。 ハムフリズ氏が提案する、初子だけを死なせるシナリオは次の通りです。エジプト人は食べ物が極端に不足していたので、雹の嵐の後に、つぶされた大麦の粒をなるべく収穫しようとしました。言うまでもなく,その大麦は濡れていて、カビが発生しやすい状態でした。ある種のカビは、環境に胞子として常在しているのですが、育つ環境が整えば、発芽して「マイコトキシン」と呼ばれている猛毒を作り出します。自暴自棄となったエジプト人が空の倉庫に濡れた大麦の粒を入れた直後に、経験したことのない激しい砂嵐の故に、三日間家に閉じこもってしまったことが十分考えられます。その間に、命を奪うほどの強い「マイコトキシン」が大麦に発生してしまいます。現代でも、そのような汚染されている穀物を食べて多くの人が急死した例があります。 この仮説が正しいとすれば、初子だけが死んだ理由は、初子にだけ食べさせたからです。当時の社会では長男の特権は多く、一般的に最初に食べさせてもらえ、また「二倍の分け前」が与えられました。ですから、暗闇のために三日間も食べられない状態から解放された後に、窮地に追いやられたエジプト人が、最初に食べ物を長男に優先的に与えたと想像しても不合理なことではありません。もし、神が目的を果たすためにこの自然現象を利用したとすれば、それは当時のエジプト人の文化を利用することも含めて、出来事の全体的な流れを組織的に導いて、自然な結末に至らせたことになります。 しかし、動物の初子の死はどうでしょうか。第一に考えるべきことは、五番目の災いによって一掃された動物の代替となる動物を連れてくる必要があったことです。しかし、災いが及んでいなかった地域から連れてくる時間があったので、それほどの問題ではないでしょう。ハムフリズ氏が仮定するシナリオは、イスラエル人と同じように,エジプト人が神々に生けにえとして捧げるために雄の初子を取り除けておく習慣があったことです。強力な権力を持っていた祭司は、神々が怒りを静めて、連続して起こる災いを取り除いてくれるように、最上の動物犠牲を要求したでしょう。動物の初子も、衰弱すると犠牲として用をなさないので、知らないうちに毒に汚染された穀物が食べさせられたと考えられます。これらの出来事は、エジプトの社会と宗教の中枢まで衝撃を与え、それ以前の災いよりはるかに強いインパクトを与えたはずです。ファラオはついにイスラエル人を手放すことを余儀なくされ、出エジプトがようやく始まりました。 紅海横断までのルート聖書学者たちが昔から首尾一貫性のある出エジプトの光景を描写することに苦労した主な理由は、後に編集されて旧約聖書の記録として保存される出来事を、モーセが注意深く記録しなかったからではありません。出エジプト記や民数記などには、出エジプトのルートや出来事等の詳細が数多く記録されています。問題は、記録された地名のほとんどが後世の学者に知られていないものだったことです。聖書のシナイ山とはシナイ半島南部にある山であるという固定観念が固く植えつけられていたので、出エジプトの実際のルートに関する推測が、その枠組みにはめ込まれたのです。 おそらく、一貫性のある光景を再現するための最も大きな問題点は紅海の横断です。原語のヘブライ語では“yam suph”(ヤム・スフ)という言葉が使用され、それは「葦の海」を意味するのに、後に「紅海」と伝統的に翻訳されるようになったのはどうしてでしょうか。紀元前3世紀にエジプトのアレクサンドリア市に住んでいた70人のユダヤ人学者が旧約聖書を初めてギリシャ語に翻訳したのですが、「スフ」は「葦」を意味することを知りながら、あえてギリシャ語の“eruthra thalassa”「赤い海」(紅海)と翻訳しました。何か理由があったはずですが、それは何だったでしょうか。(英語では,「葦」“reed”と「赤い」“red” が似ているのは全くの偶然です。) ハムフリズの著書の大きな部分を占めるのは、海を横断することに関連して「葦」と「赤い」という言葉がどのように当てはまるのか、また、聖書本文にあるいろいろな手がかりのすべてがどのように一つの場所、すなわちアカバ湾の北端に集約されていくかを探求することです。先ず、アフリカとアラビアの間にある海がなぜ「紅海」と呼ばれるかを考えてみましょう。ハムフリズ氏はアカバ湾で見た次のような光景を述べています。干潮で海水の水位が輝くように赤い珊瑚礁の上端にまで下がった時、普段は濃いブルーの海が真っ赤な大きな斑点に染まったのです。潮が満ち始めると、つかの間ではあるが、目を見張るような現象はすぐ消えるのです。その赤い珊瑚は紅海の海岸に広く生息していますので、その海が「紅海」と呼ばれたのは、この現象によるものだと推測しています。 しかし、塩水では育たない葦はどうでしょうか。「紅海」は「歴史上最も有名な誤訳」と考える学者たちは、イスラエル人が横断したのは葦が生えている内陸にある浅い湖であったという説にこだわります。その時代には、現在スエズ運河が通っている地域にそのような湖が存在してはいましたが、その地域は出エジプトの旅程ではあまりにも早過ぎるように思えます。そのような場所であるなら、スコトを出発して二日目に到着したことでしょう。ファラオが渋々許可したのは、砂漠への三日間の旅とそこでの一日の犠牲の儀式、そして、帰るための三日間、合計一週間であったことを考慮する必要があります。イスラエル人の行進があまりにも速く、そしてあまりにも遠くにまで進んだため、帰るつもりがないことが判明するまで、どのぐらいの時間が経ったかは定かではありません。しかし、ファラオが追いかけようとするまで、少なくとも二日間は進んでいたことでしょう。ファラオの軍隊はイスラエル人よりかなり早いペースで進んで行けたのですが、イスラエル人が可能の限り速く行進していたので、追いつくのにかなりの日数がかかったはずです。 こういうわけで、紅海の横断はエジプトを出てから一週間ほど後のことであることは明白です。このような時間の経過があったのなら、内陸の浅い湖をとっくに通り過ぎていたことになります。しかし、ハムフリズ氏の指摘によると、「ワジ」(雨期以外は水のない川)が流れ込むアカバ湾の奥には、海岸近くまで葦が生えている広大な地域が今日でもあります。おそらく、土地開発が進められた時代より以前には、さらに広い範囲に広がっていたでしょう。もし、その近辺で、イスラエル人が海を横断したとすれば、そこは「葦の海」と「紅海」の両方で呼ばれるにふさわしい場所だったでしょう。 「新共同訳」の聖書では、ヘブライ語の「ヤム・スフ」は「葦の海」と文字通りに翻訳していますが、口語訳などでは「紅海」となっています。この「ヤム・スフ」という言葉のほとんどは、出エジプトに関する直接的な言及の中に見られます。また、列王記上9:26にも言及されており、そこには「ソロモン王はまたエツヨン・ゲベルで船団を編成した。そこはエドムの地の葦の海の海岸にあるエイラトの近くにあった。」とあります。ここで出てくる「葦の海」とは、明らかにアカバ湾の奥(北端)で、出エジプトでの海の横断の場所としてハムフリズ氏が提案している場所と同じです。海の横断の出来事以外での「ヤム・スフ」の言及も、この同じ結論を支持します。それからかなり後の出来事を述べている民数記21:4には、こう書いてあります。「彼らはホル山を旅立ち、エドムの領土を迂回し、葦の海の道を通って行った。」エドムはアカバ湾のすぐ北の方にある地域です。また、民数記33章にある宿営の場所のリストには(33:10)、横断の少なくとも五日後に、再び「ヤム・スフ」のほとりにキャンプしたと書いてあります。アカバ湾の東側を南の方へと進んでいるなら、辻褄の合う話となります。その時代からあった通商路は、アカバ湾の東側の高原をしばらく南下してから、再び紅海の海岸に戻ります(図2参照)。 この仮説にとっての一番の難点はおそらく横断前の宿営地のリストです。というのは、記載されているのが、スコト、エタム、ミグドルの3カ所だけだからです。しかし、横断直後の旅の記述の中で,「エタムの荒れ野を三日間旅して、マラに宿営した」と書いてあるので,明らかに,次にリストされた宿営地までは必ずしも一日だけの旅を意味するのではありません。エジプト人が怪しまないように、最初の日の旅は普通の距離だけ進んで、エジプト軍の前哨基地であったスコトで宿営したと考えることは筋が通っています。しかし、その後はなるべく速く進んで行ったでしょう。彼らは、シナイ半島を横断してアカバ湾北部に直線的に続く、当時定着していた通商路を進んだ可能性が高いと思われます。そのルートに点在したオアシスでは、水補給もできたからです。満月の日に旅を始めたので、最初の一週間は明るい月が夜の大部分を照らしていました。ですから、その時期の12時間を少し上回っていた日中より、かなり長い時間安全に歩くことが可能でした。おそらく、ファラオがすぐ追いかけて来ることを恐れていたので、正式な宿営を作らずに、短い休憩時間を取りながら進んだのではないかと思います。もし、そうであれば、ファラオの軍隊が追いつく前に、6〜7日間でアカバ湾まで行けたことでしょう。 ハムフリズ氏は、次の宿営地であったエタムがアカバ湾北部の地域だったことを裏付けるいくつもの証拠を提出しています。出エジプトのルートの地名リストは、出エジプト記と民数記に記載されていますが、両者には違いが一つあります。海の横断直後に到着した地域は、出エジプト記によると「シュルの荒れ野」でしたが、民数記によると三日間をかけて「エタムの荒れ野」を通過しました。「シュル」はヘブライ語では「壁」を意味し、「エタム」はエジプト語で同じ意味です。これらは人間の手による普通の壁を意味しますが、アカバ湾から死海まで続く峡谷の両側にそびえる崖にも当てはまるでしょう。実は、この地域はモザンビークからシリアまで9000キロも走るグレート・リフト・ヴァレーの一部です。地殻変動によって、プレートが引き裂かれているので、深い谷となっています。イスラエル人が出エジプトで使用したと思われる古代通商路は、標高750メートルの高原から険しい道を下り、ワジを通過してアカバ湾の奥から数キロ南方に海岸に出ます。湾の反対側には、同じような崖のラインが北の方向にアラバ渓谷に沿って続いています。ハムフリズ氏は、1879年に出版された『ミディアンの国』というタイトルの本の中にある地図で、この「エタム」(Etham)という地名を見つけました。それはアカバ湾の真北にある「ワジ・イトゥム[エタム](Wadi Yitm [Etham])の右側にそびえる巨大な絶壁」に見える最高峰の別名であるとされていました。(図2参照) 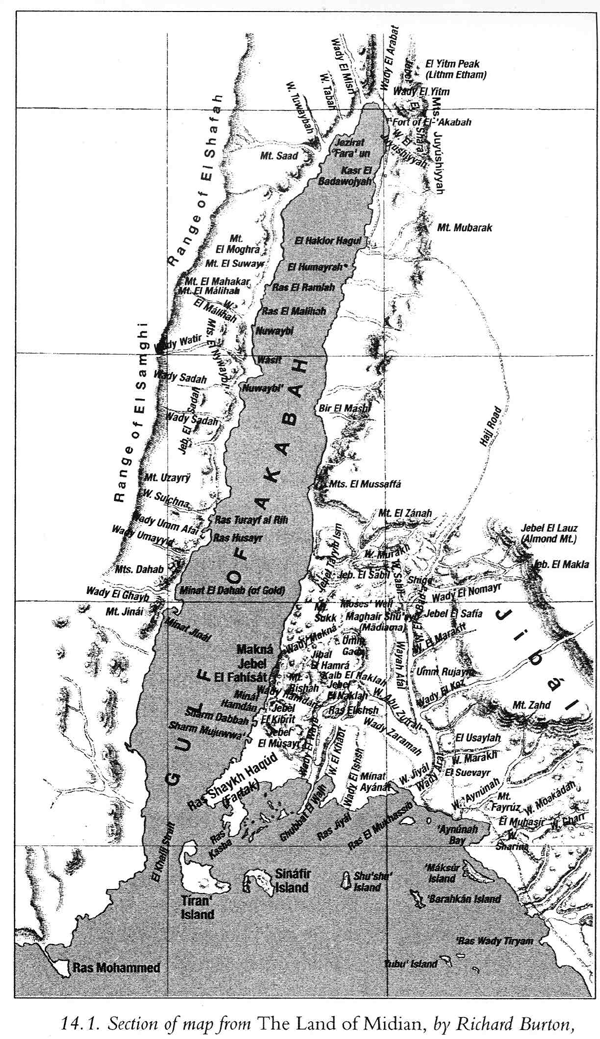 図2 出エジプト記14:2によると、エタムで宿営して後に、神はモーセに「引き返してミグドルと海との間のピ・ハヒロトの手前で宿営する」ように命令しました。これから読み取れるのは、彼らが既にアカバ湾の奥を通過しており、海を横断しないで、そのまま南の方へと進めたことです。しかし、この節に続く二つの節において、引き返す目的が、究極的な勝利をおさめることと、エジプト人が神こそ「主であることを知るようになる」ためのお膳立てであったことが教えられています。ミグドルとピ・ハヒロトは具体的にどこにあったかは定かではありませんが、このシナリオでは、湾の西側にある、通商路が高原から下って海岸に出るところと湾の奥の間になります。 シナイ半島の高原から海に下って行く道は、チャリオット(二輪戦車)にとっては、狭くて、険し過ぎることをファラオが知っていたはずです。だから、エジプト軍は二手に分かれ、歩兵はそのまま行進し、ファラオと戦車隊は北の方へ迂回して、アラバ渓谷に通ずる緩やかな坂を下ったという仮説を、ハムフリズ氏は提案しました(図3参照)。戦術的に考えれば、これは見事な作戦に思えます。というのは、イスラエル人は南西から行進して来る歩兵と北東から襲って来る戦車隊の間に挟まれる結果となるからです。そして、実際に宿営していた場所にもよるのですが、西や北西側の絶壁と東や南東側にある海の間に閉じ込められることになりました。 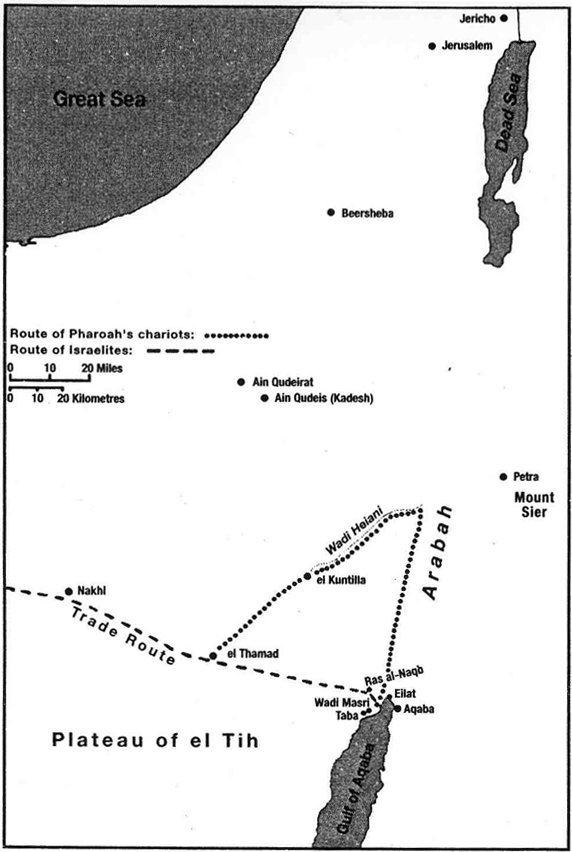 図3 聖書本文によると、エジプト軍が追いついた時はちょうど夕暮れだったので、イスラエルの民を再び捕らえるのを次の朝まで待ったと考えることは自然な解釈です。出エジプト記14:19-20に記されているように、神の御使いとその「雲の柱」がイスラエルの民とエジプト軍の間に立ったという出来事は、どのような自然現象としても、たとえそれが神によってコントロールされたとしても、説明することは困難なことです。このことが何から何まで完全に神による超自然的な出来事であったのか、それともイスラエルの民をエジプト軍から守ってくださった神の配慮を表す詩的な表現なのか、分かりません。もし詩的な表現であるとすれば、出エジプト記は一般的には「詩的な表現」を利用していないので、例外となります。とにかく、この出来事がエジプトを出て七日ぐらい後の話であれば、月が昇るのは午前0時以降となったので、夜の前半は真っ暗だったはずです。 紅海の横断これで、出エジプトのクライマックスのお膳立てができました。神は「激しい東風」を一晩中吹かせて、海を押し返しました。水が突然に分かれて,乾いた地面の両側に絶壁となるというハリウッド映画のイメージが心に焼きついていますが、それは聖書本文にほのめかされている意味とはまったく異なっています。それどころか、海の水を押し返すのにおよそ12時間吹き続ける強い風が必要でした。これは「wind setdown」(風による水面下降)として知られる現象なのです。強い風が長時間広い水域の上に吹き続けると、風下へと水が押されるので、風上側の水位が下るという現象です。これは台風による高潮と同じメカニズムで,その場合,陸に向かう暴風が海水をかなり内陸まで押し上げるのです。 一瞥したところでは、東風という記述は問題があるように思えます。というのは、アカバ湾は北北東から南南西へと走る細長い湾ですから,東風は相対的にほんの一部になります。しかし、ハムフリズ氏が指摘するように,古代イスラエル人は四つの基本方位しか使わなかったので、「東風」は北東と南東の間から吹く風という意味になります。この「風による水面下降」という自然現象で出エジプト記に記述されている状況を説明するには、アカバ湾全域を吹く北北東に近い強い風が必要です。 このような風は「北風」であると見なされるべきであるように思えますが、イスラエルの民が具体的に海岸のどの辺にいたか、また湾のどの部分を横断したかはっきりしないので、必ずしもそうではありません。湾の奥の海岸の輪郭や湾全体にそのような風を起こすために必要な気圧配置を考えますと、彼らが横断直前にいた場所では、北東より少し東よりの風向きが最適だった可能性があります。こういう場合、基本方位を使用すれば、「東風」となります。 大気の仕組みから考えると、必要な気圧配置とは、湾の奥の北北西にある高気圧と南南東にある強い低気圧の間に、込み合っている等圧線です。そのような配置なら、湾の奥当たりで北東の風(低気圧の方向へ、低角度で等圧線を横切るように)が吹くことになり、南に行けば行くほど北風へと変わります(図4参照)。さらに南に行くと,風の向きはだんだんと西風へと変わりますが、それは湾の入り口また紅海の近辺になるでしょう。ですから、湾の奥当たりで,東北より少し東よりの風で始まり,南の方へ行けば行くほどに北風に変わっていく気圧配置は決して考えにくいことではありません。その上,両側に走っている高いがけが、風方向をある程度それに沿う方向に強いるのです。一晩中吹くそのような強い風は著しい「風による水位下降」を引き起こし、海底を何百メートルもの沖合まで露出させます。海底の傾斜が小さいのであれば、特にそうなるのです。 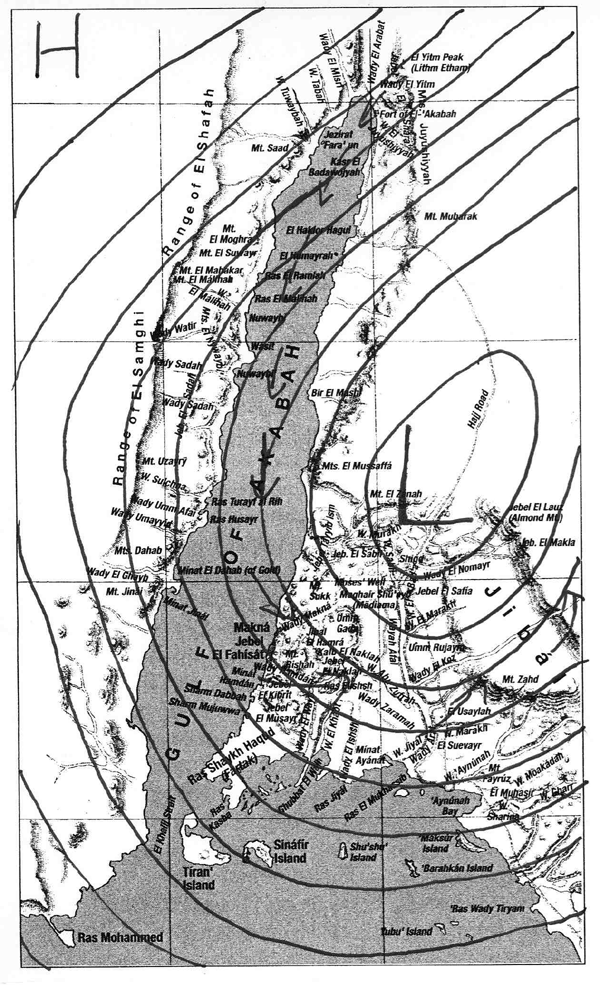 図4 しかし、この説には問題点もあります。出エジプト記によると、水は乾いた地の両側にありました。ですから、この「風による水位下降」で説明するためには、湾を横断して対岸まで走っている海底の峰が必要です。このような憶測の信憑性を裏付けるためには、実際の地形と比較する必要がありますが、3300年も経った現在の海岸はモーセの時代のものとかなり変わった可能性があります。ですから、そのような峰を発見できなくても,その時代にもなかったと限りません。しかし、現在にも湾の奥にそういう海底の峰が存在しているなら、この仮説にかなりの信憑性を与えます。 両側に立った水の「壁」の問題に関しては,「風による水位下降」によって露出した海底の峰という説を採用するとしても、その水の「壁」は風下にしかできません。「壁」と翻訳されたヘブライ語は町や家の壁と同じ単語ではありますが(ただし、絶壁という「壁」を意味する「シュル」とは違う単語ですが)、それは必ずしもほぼ垂直に立つ水の「壁」だったと意味ではありません。重要なのは横断したところに水が両側にあったということです。原語を直訳すると、「水が右側に壁となっていた」(つまり、風下側)となりますが、「左側」はただ、それに付記されているだけで、水はどんな形となっていたかについて直接的な言及はありません。もし「壁」が「障壁」を意味するなら、その「壁」の形は問題ではありません。しかし、風に支えられたほぼ垂直な水の壁と考えても、左側もそうだったとは直接に書いてありません。物理学的なメカニズムでは、どんなに強い風でも両側に水の「壁」を作ることはありません。ただし、横断のルート全体に真上から吹き下ろす風が地面にぶつかって横に広がる風であれば別ですが、そのような風を起こす自然現象はありません。そういうシナリオであれば、完全に超自然的な現象となります。しかし、聖書本文には、この状態になるまで、一晩中吹く風が必要だったことがはっきりと書かれています。もし神様が自ら創った自然法則を越えて、このような超自然的なメカニズムを利用するなら、それは数秒でできたはずです。(ハリウッド映画のように!) 大波となって戻る海水が兵士や彼らの馬を投げ倒すほどに強い衝撃を与えるメカニズムが何であったかはいくつかの可能性があります。イスラエル人が海岸のすぐ近くを横断していたとすれば、エジプト軍が海岸に沿って迂回し、対岸でイスラエルの民の行く手を遮る方が当然あり得ることです。しかし、聖書本文には、神が「エジプト軍をかき乱された」と書いてあります。まだ夜明けには間があったので、上空にある半月しか光はありませんでした。さらに、強い風のせいで、空気中に埃が舞い上がっていたことでしょう。そして,「戦車の車輪をはずし、進みにくくされた」ので、エジプト軍は大混乱に陥ったことでしょう。 神が大波によってエジプト人を撃破したのは夜明けだったと、聖書本文が述べています。この現象を起こした原因の一つとして考えられるのは、月が上空の頂点に達していたので、満潮の時間と重なり、風圧で押さえつけられていた水の壁の裏にかかっていた圧力が増していたことです。原文には、風が止んだとは書いてありません。ただ、「海は元の場所へ流れ返った」と書かれているだけです。水の壁を支えていた強風が突然に止んだ場合、その水が元の海岸線まで戻る速さを、ハムフリズ氏は計算しました。その速度は時速17キロメートルでした。それは、既にあった浅い水の中を海岸の方向に逃れようとする兵士に追いつくには十分なスピードです。もちろん、大きな低気圧によって発生した強い風が突然に止むことは自然界では通常起こるものではありません。しかし、限定された地域では起こり得ることです。例えば,数キロ沖合に強い雷雲が発生すると、強烈な「マイクロバースト」(突風が下降して地面に叩き付けられた後、広がって行く現象)が、彼らがいた狭い範囲全域において、東風を相殺したことが考えられます。 しかし、出エジプト記の記述では、風が止んだとは書いてないので、神は、突然の水の流入という別な自然現象を利用した可能性もあります。大波が南からちょうどいいタイミングで襲ってきたとすれば、説明がつきます。例えば,アカバ湾の南部で地震が起こり、モーセが海の方に手を上げた瞬間に津波が到達するように神が操ったかもしれません。どのような物理的なメカニズムを通してであったとしても、ファラオの「えり抜きの戦士」が溺れ死んだ(出エジプト記15:4 ;これはファラオ自身が死ななかったことを暗示しますが)という神の目的が成就しました。 シナイ山は噴火していた火山だったでしょうか。エジプト人に追いかけられる心配がなくなったイスラエル人は、目的地であったシナイ山に到達することだけに焦点を合わせることができるようになりました。ハムフリズ博士は、シナイ山が噴火していた火山であったという結論を裏付ける聖書の多くの記述をリストアップしています。彼の結論が正しければ、― 私はそう信じているのですが ― 本当のシナイ山がどれだとしても、活火山であるはずです。シナイ半島には、そういう活火山は一つもありません。地質学的に言えば、最近活動したことのある火山は古代の国ミディアンの近くで、サウジアラビアの西部にしかありません。それはエジプトから逃亡したモーセが住んでいたところと同じ地域なのです。 モーセの「神の山」における最初の経験は、「燃える柴」を目撃した時でした。そこで、彼は生ける神と出会ったのでした。それは、単に柴の枝が燃えている以上の現象であって、柴の中で実際に燃えている炎として描写されています。ハムフリズ氏の説明によると、これは生きた柴の下に開いた割れ目から、加熱された天然ガスが漏れ出したことによる現象で、天然ガスや石油が存在する火山活動の地域に十分考えられることです。空気に触れた天然ガスは引火し、柴がまだ枯れていなかったとすれば、モーセが目撃した光景の通りのことがあったはずです。即ち、柴が燃えていても、すぐには燃え尽きることはないのです。 エジプトを出てから、昼は「雲の柱」が、そして夜は「火の柱」がイスラエル人を導いてくれました。これは前に進んで行く竜巻として描かれていますが、ハムフリズ氏が指摘したように、彼らの前に動いていたというふうに書かれているのではなく、「民の先頭を離れることはなかった」としか書いてありません。それは遠くから見えた火山の噴火を意味する表現だと考えています。噴火しているベドゥル山から舞い上がる「雲の柱」は澄んだ砂漠の空にシナイ半島の東部から容易に見ることができます。そして、その方向は、彼らの進んでいた方向より少し右にありました。 出エジプト記14:19-20にある「彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち」という記述の難点を説明するために、その箇所の意味を、アカバ湾に下りて北に方向を変え、湾の海岸線に沿って進んだと解釈します。すなわち、エタムに宿営した後に、「引き返す」(英語の訳は「後ろに向く」)という表現は、ただ雲の柱が彼らの後ろとなるように左に向きを変える意味だと解釈します。もし、エタムという宿営地がアカバ湾に下りて行く行程に先立ってあったとすれば、この解決は可能だと思います。しかし、横断直前の夜、エジプト軍とイスラエル人の衝突を防ぐために、雲の柱が彼らの間に立ったという記述を説明できず、エタムはアカバ湾の奥にあったというハムフリズ自身の結論と合致しません。ですから、「雲の柱」とは、シナイ山の噴火によって柱のように立ち上る雲であるとする説明は、面白い仮説ではありますが、出エジプト記14:19-20を十分に説明できなないので、出エジプトのこの点について結論するのはまだ早いでしょう。 「雲の柱」の描写が火山の噴火で説明できるかどうかは別にして、彼らが経験した他のことを説明できるのは明らかなことです。申命記4:11の記述は、噴火する火山の描写そのものです。「あなたたちが近づいて山のふもとに立つと、山は燃え上がり,火は中天に達し、黒雲と密雲が垂れこめていた。」出エジプト記19:16-19にも噴火を描写するいくつもの現象が記録されています。地震、厚い雲から走る稲妻、また「角笛の音」(これは適当な形状を持つ狭い穴から吹き出る高圧ガスが起こす音)などです。 「シンの荒れ野」ハムフリズ氏は、出エジプトに関して他にも数多くの項目を取り扱っていますが、ここでは、その一部だけに触れることにしましょう。(英語を読める方はhttp://www.europhysicsnews.com/full/33/article6.pdf に参照。)例えば,「天からのマナ」の描写は、適当な条件下で、砂漠に生息する”ギョリュウ(御柳)”(タマリスク)という木の下に現れるものにそっくりです。イスラエル人がマナを初めて食べたのは「シンの荒れ野」です。ハムフリズ氏は、いくつもの証拠を示して、それがミディアンの「ヒスマ砂漠」(サウジアラビア西部、図1参照)であると結論しています。そこには数多くのギョリュウの木が生息しています。そして、春になって多くの水が供給されて、多くの樹液が作られるようになると、虫などに咬まれたところから樹液が染み出てきます。そして、「霜のように」「荒れ野の地表を覆って、」「コエンドロの種に似て白く,蜜の入ったウェファースのような味がした」ものになります(出エジプト記16:14, 31)。さらに、鶉(ウズラ)が南アラビアで冬を過ごして夏の生息地であるヨーロパに帰る時に、四月をピークにアラビア西部を飛んで行きます。イスラエル人が「シンの荒れ野」に着いたのはエジプトを出てちょうど一ヶ月後でしたので、それは4月末か5月初め頃となるので、鶉がその地域を移動する期間と重なるのです。 ハムフリズ氏の本で最も面白いのはおそらく、シナイ山で起きた出来事と「月の神」信仰との関連を指摘したところです。この「シン」という名前は古代バビロニアで信仰された「シン」という月の神に由来していると、多くの聖書学者の一致した見解を裏付けるいろいろな証拠を紹介しています。近くの古代都市タイマがこの宗教の拠点であったことが証明されており、他の証拠と合わせると、古代アラビアでは、神々の中で月の神が最も崇められていた神であったとことが分かります。(図5参照。タイマはベドゥル山より120キロメートルほど東にありました。) 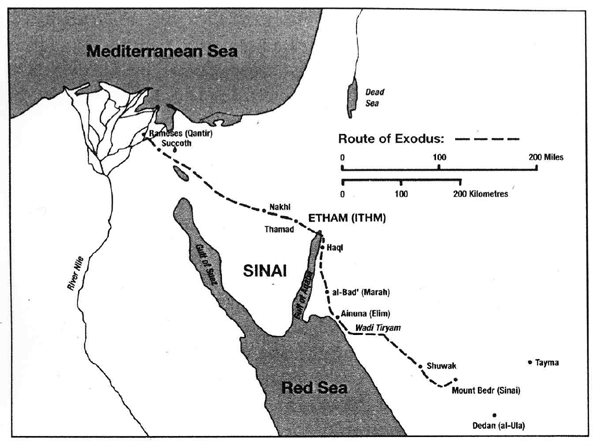 図5 ハムフリズ氏は、ヘブライ語学者であったジェムズ・モンゴメリィ氏が書いた「アラビアと聖書」という本から次のように引用しました。「南アラビアでは、天体の三柱の最高神が際立っていました。即ち,月と太陽と明けの明星あるいは宵の明星(金星)です。その中で、より古いバビロニアの宗教と同様に月が卓越していました。それは定住生活を営んでいた農業社会が太陽を中心に活動を始める以前のことでした。」面白いことに、イスラム教の象徴の一つである三日月と一つの星は、イスラム以前の古代宗教の名残のようです。まれな現象ではありますが、夜明け前また夕暮れの空に明るく輝く金星と三日月がそのように並ぶことがあり、そのような接近は月の神シンを拝んでいた古代人にとって、極めて重要な出来事であったはずです。 「シナイ」(Sinai)は、「シン」(Sin)という名前と関係があるのでしょうか。ハムフリズ氏は、説得力のある論拠を述べています。ヘブライ語では、「アイ」(ai)という接尾辞が「から」や「の」、あるいは「に属する」というような意味を持つので、イスラエル人がその山を「シナイ山」と名付けたのは、おそらく「月の神シンの山」と意味したのではないかと思われます。モーセの義理の父エトロは「ミディアンの祭司」であって、別な神の祭司であった可能性も否定できませんが、月の神の祭司であった可能性が高いのです。出エジプト記3:1にモーセがエテロの羊の群れを「神の山ホレブ」に連れて行って、「燃える柴」を見たと書いてあり、出エジプト記18章にはエテロ自身がモーセに会うためにこの同じ山に来たことが記されています。そこで、彼が「私は、主が他のすべての神々より偉大であることを知った」と宣言し、神に犠牲を捧げたのです。このようなヤハウェへの忠誠に回心したことが完全なもので継続したかどうかはわかりませんが、自分のところに帰る前に主なる神の霊に導かれて、モーセにとても良いアドバイスを与えることができました。 この山のアラビア語の名前は「ベドゥル」で、それは「満月」という意味です。頂上の火口の輪郭はきれいな円形であり、山そのものは富士山を小さくしたような形状で、平らな広い高地の上にそびえています。この山が神聖なものと考えられたのは想像に難くありません。また、頂上の「満月」様のクレーターのゆえに、これが月の神シンを祀る山として選ばれたのは自然の成り行きでした。その広大な溶岩地帯にある、その近辺の他の火口とは違って、ベドゥル山は孤立した円錐状の形をしており、幅5 km 、長さ10 kmの標高1500mの、頂上が平らになっている「タドラ」という山の東端に、さらに180m高くなっています。この台地は太古の砂岩でできていますが、ベドゥル山の火口丘はそれを突き破ってできたものです。以下のインターネットのサイトでは、その山の衛星写真を公開しています。 タドラ山の画像を公開しているサイトに掲載している写真は白黒で、楕円形をした灰色の台地の右端(東端)に、円錐状の火山が見えます。火口丘の左側に細長い白っぽい場所が映っています。これはおそらく植物があまり生えていない真っ平らな土地です。3300年前にこの場所がどのような状態だったかは分かりませんが、山の近くに幕屋を建てたり、長期の宿営を行ったりする場所としては最適だったでしょう。卓越風が火山灰を反対方向に運んだので、火山の西側は比較的に安全な場所となります。 もう一つ の衛星写真はカラー写真です。台地が青っぽく映っているので、草木が比較的に多くあることが分かります。火山丘は薄茶色となっています。 ベドゥル山の地形は、民も動物も侵入を許さない「聖地」の境界線を描きやすいものとなっています。ハムフリズ博士は、アロイス・ムシルという探検家の「北ヘガズ」という本を引用して、100年ほど前にこの地域で経験されたことを紹介しています。その地域の遊牧民はベドゥル山に登ることを恐れて,群れをその近辺で放牧させないということでした。ムシル氏は、ベドゥル山の北側に12の石が並んでいる祭壇について述べており、遊牧民が「今でも、その近くに野営する時、生けにえを捧げる」と報告しています。もしかしたら、これらの石は出エジプト記24:4に述べられているものと同じ石かも知れません。「モーセは主の言葉をすべて書き記し,朝早く起きて,山のふもとに祭壇を築き、十二の石の柱をイスラエルの十二部族のために建てた。」 残念ながら、この地域では地質学的、考古学的調査が許可されていません。ですから、このような推測を裏付けるのは、衛星写真や昔の探検の記録などに制限されてしまいます。この山の近辺に出エジプトの遺跡が実際に存在するのか、また火山活動が該当する時期にあったのかを調査することは、この仮説を裏付ける(また、それを反証する)確実な証拠を提供します。サウジアラビア政府がそれを許可しない理由として私が推測することは、石油収入の多いサウジでは、シナイ山の発見が引き起こす観光ブームによる外貨収入の必要性を感じないばかりか、神が嫌われ者のユダヤ人を特別に守って導いたというこの話に信憑性を与えることは歓迎しないということでしょう。 最後に、「金の子牛」事件に対するハムフリズ氏の本からの引用で締めくくりたいと思います。「シナイ山とはベドゥル山であったということが、出エジプト記に記録された金の子牛事件という好奇心がそそられる出来事をよりよく理解させてくれます。その背景には、モーセが火山煙に覆われていたシナイ山に登って、四十日四十夜が経っても誰も見ていなかったことがありました。出エジプト記32:1によると、イスラエル人がアロンに言いました,「さあ、我々に先立って進む神々を造ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのか分からないからです。」しかし、彼らが考えていたことは、私たちも想像できます。モーセが月の神の山に登って行方不明となりました。イスラエル人は、月の神がモーセとモーセの神に勝って、モーセがこの恐ろしい山の頂上で殺されたと思うようになったのでしょう。ですから、イスラエル人は彼らの神が自分たちのためにしてくださったことを忘れて変節し、月の神を象徴する偶像を作って崇拝しました。バビロニアから南アラビアまで分布していた月の神の神殿に刻まれていた、月の神を象徴する動物は何だったでしょうか。メディアンのタイマで発掘された彫刻(写真参照)で見られるように、それは若い雄牛、つまり子牛でした。」 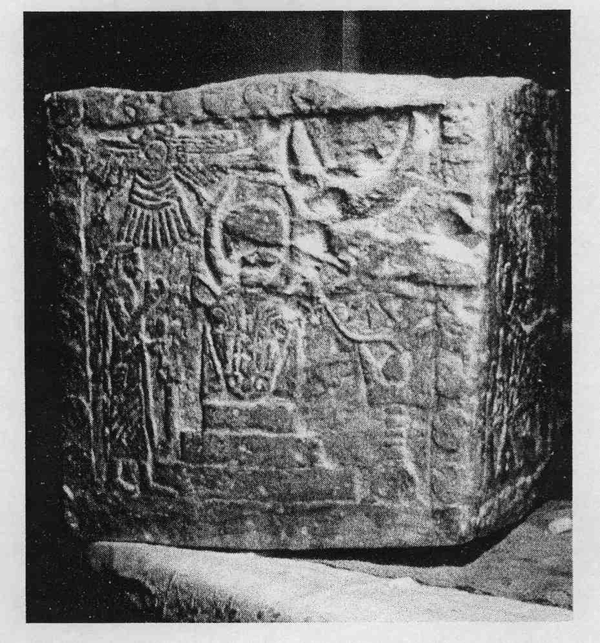 写真:紀元前6世紀のタイマ・キューブ。雄牛の頭部と三日月の形となっている角、そして、右上の三日月に注目。 |
